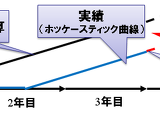TAM、SAM、SOMとは?
TAM/SAM/SOMは、新規事業やスタートアップに関わっていると良く出てくるキーワードの一つで、「市場規模」を表すものです。
市場規模は、新規事業開発においては極めて重要な指標の一つです。ところが、何を「市場」と定義するかによって、ファンタジーなほど膨れ上がったり、何の魅力も感じられないほど小さくなってしまったり、新規事業を進めるうえで意外に取扱いが難しい指標でもあります。
そこで、市場規模を分けて整理するとより検討がしやすい、ということで、1990年代後半のドットコムバブル期のアメリカ西海岸あたりで考え出された概念がTAM、SAM、SOMです。それぞれは次のように定義されています。
TAM:Total Addressable Market
製品やサービスが理論上すべてのお客様に届いた場合の市場規模
SAM:Serviceable Available Market
(TAMの中で)自社がサービスを提供可能な市場規模。地理的、製品特性的、法的な制限も加味して設定する市場規模
SOM:Serviceable Obtain Market
(SAMの中で)競合環境や自社の実力地も加味して実際に獲得できそうな市場規模
この3つの指標で市場規模を分けて考えることで、「何の話をしているか」が明確にわかるようになります。
TAMは何に使う指標なのか?
TAMが表すのは、「理論上の最大市場規模」です。これは言い換えれば、このビジネスを行うとした場合に、TAM以上の売上にはならない、ということを示すものでもあります。
上場クラスの大企業で新規事業を検討する場合、「100億円以上の売上を目指してほしい」というリクエストが良くあります。100億円まで行かないとしても、おおむね、売上10億円以上でないと「事業」として認められない企業が多いのではないでしょうか。そのため、TAMがあまりにも小さいとそもそも「この事業案は無理」ということになります。
新規事業開発の支援をしていると、たまに「あまりにも事業規模の小さいビジネスプラン」が出てくるケースがあります。市場規模が小さいと、どの様な検討をしたとしても大きな売り上げは見込めませんので、足切り基準として使いやすい指標です。
また、TAMが表す市場の成長性も一つの目安になります。SAMやSOM自体がまだ市場成長を見せていないとしても、TAM全体が伸びている場合、事業そのものも伸びやすい場所にあることが多いです。
では、TAMはどのように算出するのでしょうか?
「一般的に市場規模が何らかの形で示されているケース」と「どこにも記載がないケース」があります。
「一般的に市場規模が何らかの形で示されているケース」とは、例えば、国の統計資料やシンクタンク、調査会社のレポートなどに市場規模が記載されているケースです。〇〇業界レポートなどに書かれている数字もこれにあたります。厳密には、検討をしている新規事業の「理論上の最大市場規模」よりも小さく示されているケースも多いのですが、事実情報として開示されているがゆえに分かりやすい指標になりえます。従い、これらの統計情報を使うこともあります。
もう一つの「どこにも記載がないケース」ではフェルミ推定のような計算を行います。客数×客単価をベースとして、「客単価を〇〇円と想定し、想定されるユーザが〇〇人(または社)いるのでこれくらい」という算数を行うものです。例えば、日本の自治体(市区町村)向けに単価100万円のサービスを提供する場合、TAMは1,718自治体×100万円 =約17億円、と見積もられることになります。
SAMは何に使う指標なのか?
SAMは「自社がサービス提供可能な市場規模」です。言い換えると「市場シェア100%になった場合の売上」にあたります。SAMとSOMはセットで考えると分かりやすくなります。SAMは短期的な事業の売上に直結しやすい市場規模を示し、(後掲のとおり)SOMはそのSAMの中で自社がどのくらいのシェアを獲得できるかを示す指標です。
SAMは、自社の顧客が具体的にどこになりそうなのか、というセグメンテーションの考え方とセットで考えるのが一般的です。例えば、このサービスはそこそこ予算規模がないと導入されない、例えば、自治体だと10万人以上の規模しか使わない、とすると、SAMは、280自治体(10万人以上の人口)×100万円=2.8億円、ということになります。
SAMの算定については、新規事業の場合は統計情報などが通常存在しないので、自分で計算することになるのが基本でしょう。
SOMは何に使う指標なのか?
SOMは「実際に獲得できそうな市場規模」です。事業計画における「売上」がそのままSOMになります。
SOMは、「実際に獲得できそう」な規模なので、競合との立ち位置あるいは自社のリソースを考えたうえでSAMの中で自社はどこまで獲得できそうか、を考えるものです。従い、事業計画の売上計画を作成して出来上がった数字がSOMになります。
なお、SOMというと「Market」とあるので市場規模のようにも見えますが、現実に使う場合は目標売上、くらいの感覚です。
TAM、SAM、SOMを投資の判断基準として使う場合のポイント
TAM/SAM/SOMは、事業を作るイントレプレナー側にとって重要な考え方ですが、どちらかと言えば評価する側、例えば、新規事業投資を行う役員が投資判断に使う方が利用目的としては多いのではないでしょうか。
その時に、単に「市場規模」と見るのではなく、
- TAM:どれくらい拡大余地がある、投資すべき市場領域か? → 魅力的な市場なら将来のPivotも見据えて投資はアリ。逆に魅力がなければ、この時点でSTOP
- SAM:この事業はMAXいくらになると思っているのか? → Pivot前提なのか、今のプランを磨くのか、の判断
- SOM:計画の蓋然性が高いか、(会社基準から考えて)投資回収できそうなモデルか?
という見方をされると、より使い勝手が良いのではと思います。